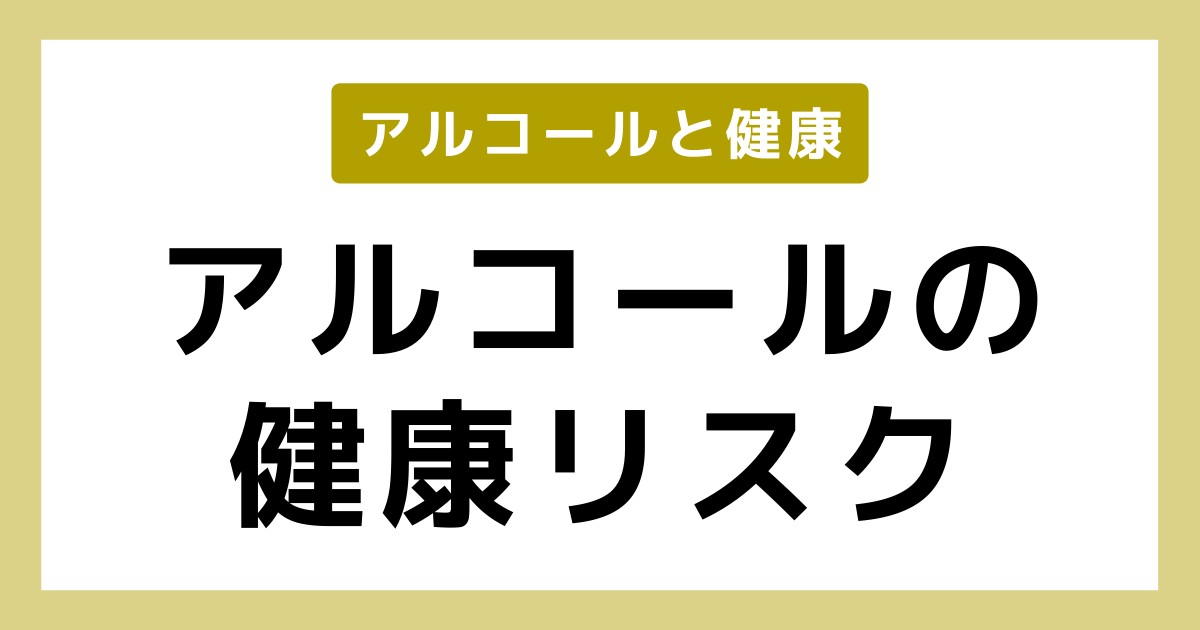◻︎
【アルコールと健康】#3 アルコールを減らす・やめるこつは?
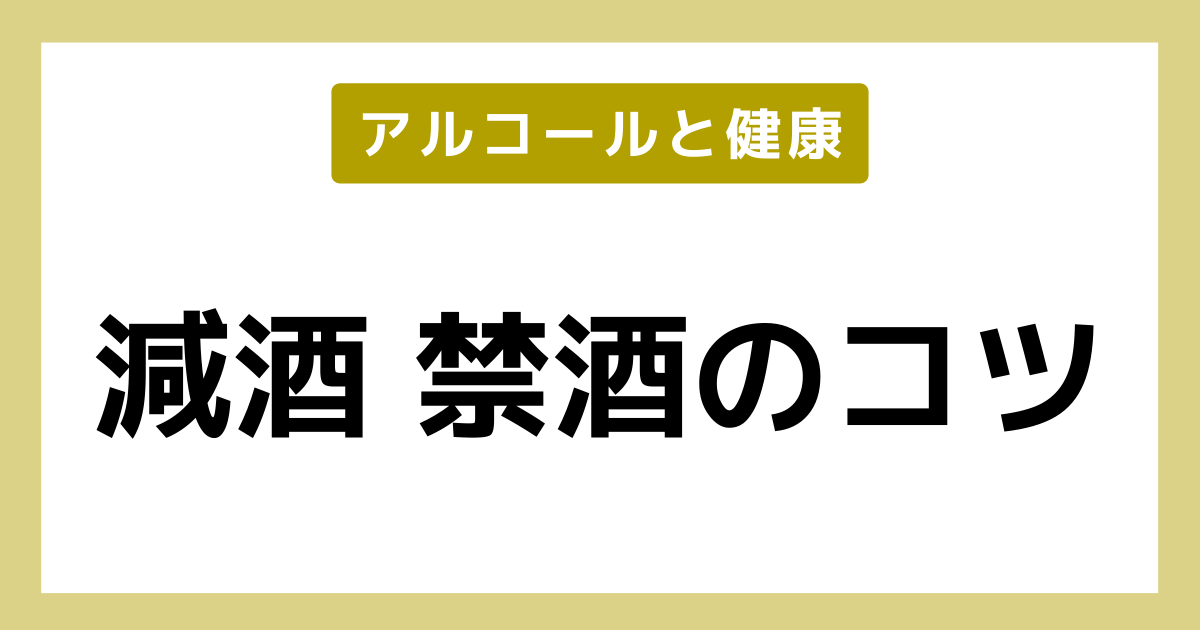
アルコールを飲む習慣があり、毎回エタノールにして20gを超えるような量を飲んでいる方はぜひアルコールを減らしたり、やめたりすることにチャレンジしましょう。
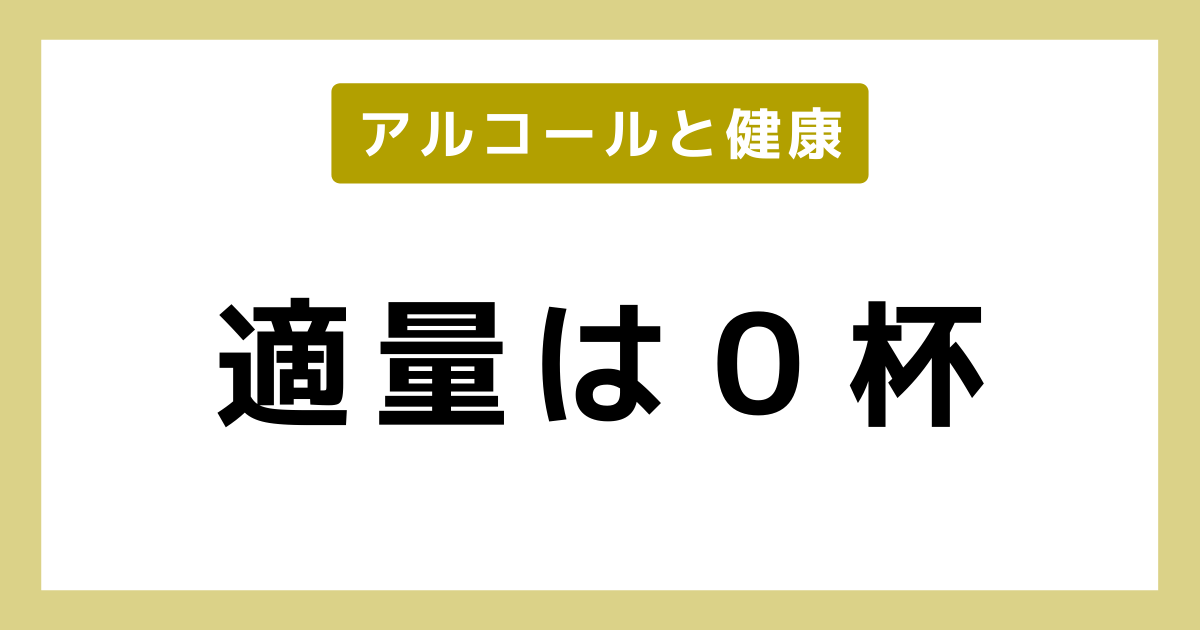
お酒を控えることは、決して「楽しみを奪うこと」や「我慢を強いること」ではありません。むしろ、自分の体や心の声に耳を傾け、将来の健康や日々の快適さを大切にするための前向きな選択です。
「今日は飲まなくてもいい」「たくさん飲まなくても十分楽しい」──そんなふうに感じられるようになると、生活のリズムも整い、翌日の目覚めがスッキリしたり、体の調子が軽くなったりと、思わぬ良い変化が訪れるかもしれません。
スマドリ習慣:多くの人が始めています
「スマドリ」とは、「スマートドリンキング(Smart Drinking)」の略語で、お酒との付き合い方をスマートに考えようというライフスタイルや考え方のことです。
- 自分に合った飲み方を選ぶ:アルコールの強さや体質、気分、シチュエーションに応じて、無理に飲まず、自分にとって心地よいスタイルを選ぶ。
- ノンアルコールや低アル飲料も選択肢に:お酒を飲まない・飲めない人でも楽しめるように、ノンアルコールビールやモクテル(ノンアルカクテル)などの選択肢を尊重。
- 飲まない選択もポジティブに:断ることや飲まないことを「失礼」とせず、誰もが自由に飲酒の有無を選べる社会を目指す。
- 多様性の尊重:アルコールに対する考え方・体質の違いを受け入れ、誰もが気持ちよく過ごせる場をつくる。
スマートドリンキングという考え方の広がりにより、ノンアルコールや低アルコール飲料など、自分に合ったスタイルを選べる時代になってきました。
大切なのは「飲む」「飲まない」ではなく、“どう自分らしく付き合うか”という視点です。
お酒を減らすという行動は、心身の健康はもちろん、仕事や家庭、自分の人生そのものをより良い方向へと導く一歩になります。
我慢ではなく、自分を労わる習慣。
それが、アルコールとのスマートな関係のはじまりです。
飲酒をやめたら良いこといっぱい
すぐに改善を実感できること
アルコールを飲む習慣をとめてみると体調が良くなることを実感できます。特に睡眠の質が改善することで、目覚めが良くなり、日中のパフォーマンスが上がるでしょう。
比較的すぐに感じる変化
- 目覚めが良い
- 胃の調子がよくなった
- 仕事のパフォーマンス改善・集中力が上がった
- 血圧が下がった
- 体重が減った
- 肝臓の数値が改善した
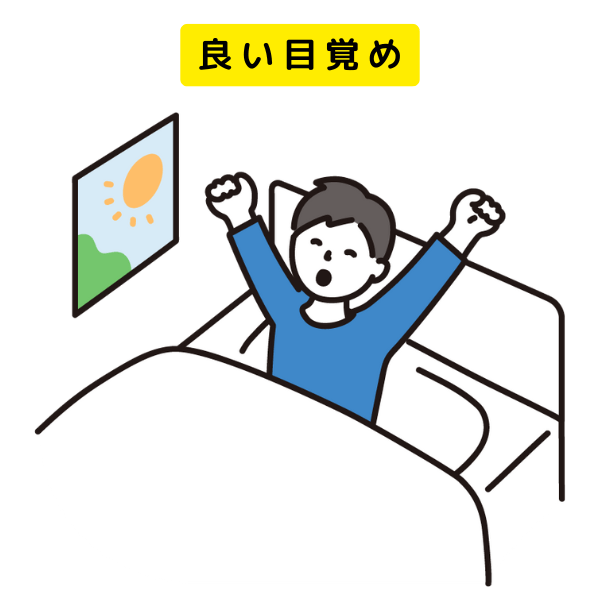
健康寿命が伸びる
飲酒習慣により下記のような多くの病気を引き起こす可能性があります。
アルコールを減らす、やめることは病気の発生を抑え、健康な状態を維持するのに良い影響を与えます。
自宅での飲む量を減らすポイント
アルコールをストックしない
自宅に常備しているアルコールを自動的に補充する習慣から抜け出しましょう。
いくら強い意志で禁酒を誓っても、目の前にアルコールがあるとついつい手が伸びてしまいます。まずは環境を整えましょう。
買い物の際にアルコールを多めに買うのをやめましょう。在庫がないと心配かもしれませんが、なければ飲むのを諦めましょう。
もしくは週にビール350mlを5本だけ飲むなど、決めて購入しましょう。
ノンアルコール飲料を試す
最近ではアルコールフリーのビールやカクテルが多く販売されています。炭酸系の飲み物は清涼感があって、飲んでいる感じがするでしょう。
多くの種類があるので、自分に合ったノンアルコール飲料を探しましょう。
または、ビールを3本飲む習慣がある方は、2本目はノンアルコールにしてみるなどで、アルコール摂取量を減らすこともできます。
飲まない日を作る(逆に、飲む日を決める)
飲まなくても生活できることを実感するために、全くアルコールを飲まない日(曜日)を決めましょう。生活の一部となっている飲酒ルーティンを生活から外す練習です。
飲まない日を作ることができたら、今度は飲む日を決めましょう。例えば、週に金曜と日曜は飲む日にする、などです。
とにかく、生活の一部となっている飲酒習慣を変えていきましょう。
早い時間から飲まない
飲み始める時間帯が早ければ早いほど、合計で飲む量が増える可能性が高くなります。
休みの日などに昼から飲んだりすると、1日の飲酒量が多くなります。飲むとしても、前倒しで飲まずに夕食まで待ちましょう。
周囲の人にも協力してもらう
家族やパートナーと一緒に住んでいる場合は、協力してもらいましょう。アルコールを減らす、やめる決意を、ご家族やパートナーと共有しましょう。
他の楽しみを見つける
飲酒を習慣にしている方は、「今日帰って飲むぞ」というのが日々の活力になってしまっていることも少なくありません。
飲酒が日々の唯一の楽しみにならないようにアルコール以外の楽しみ(読書する、ドラマを観る、散歩するなど)を見つけることができたらより効果があります。
『アルコールと健康』シリーズ
基礎 編
-

【アルコールと健康】#1 アルコールの健康リスクとは
以前から、アルコールは飲みすぎると良くないが、多少ならむしろ良いと言われてきました。しかし、最近になって少しのアルコールでも飲まないよりも有害であることが示… -


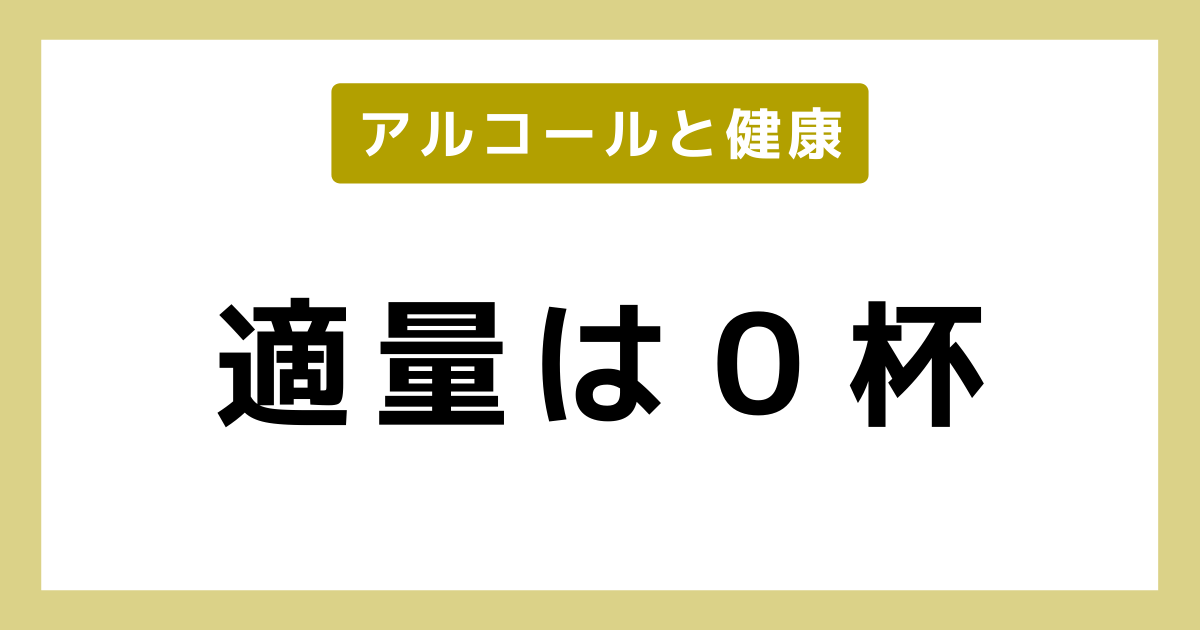
【アルコールと健康】#2 アルコールの適量はゼロ?
アルコールはできるだけ飲まない! アルコールは飲まないことが最適で、飲むとしても20gを超えないこと! 厚生労働省は、「健康日本21」のなかでアルコールの量について… -


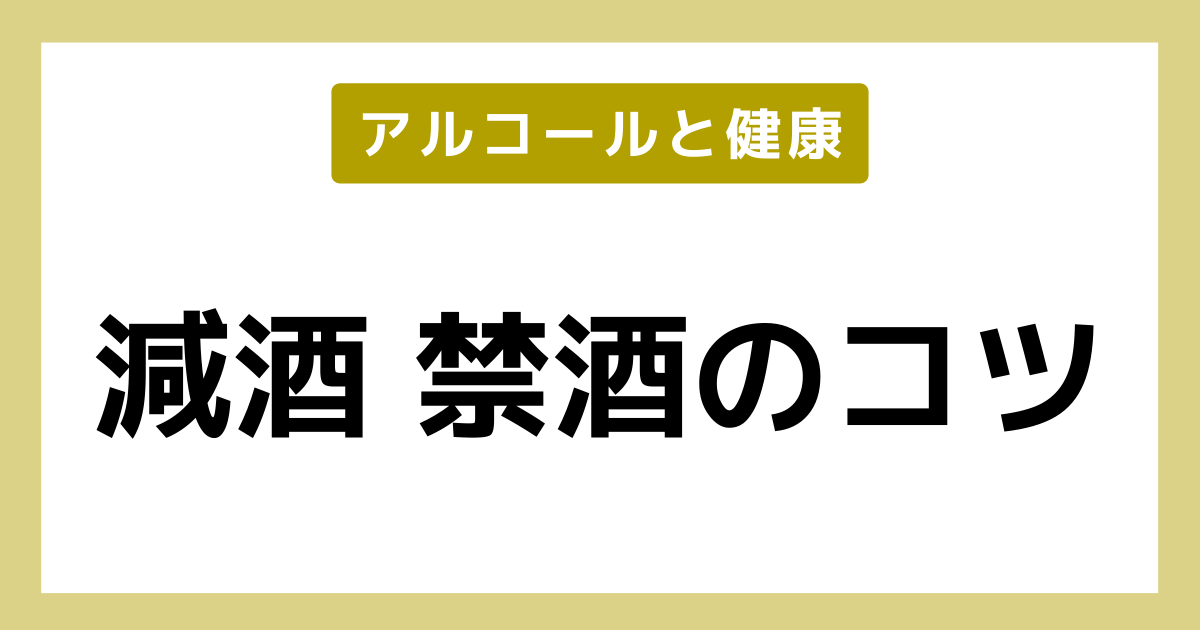
【アルコールと健康】#3 アルコールを減らす・やめるこつは?
アルコールを飲む習慣があり、毎回エタノールにして20gを超えるような量を飲んでいる方はぜひアルコールを減らしたり、やめたりすることにチャレンジしましょう。 お酒… -


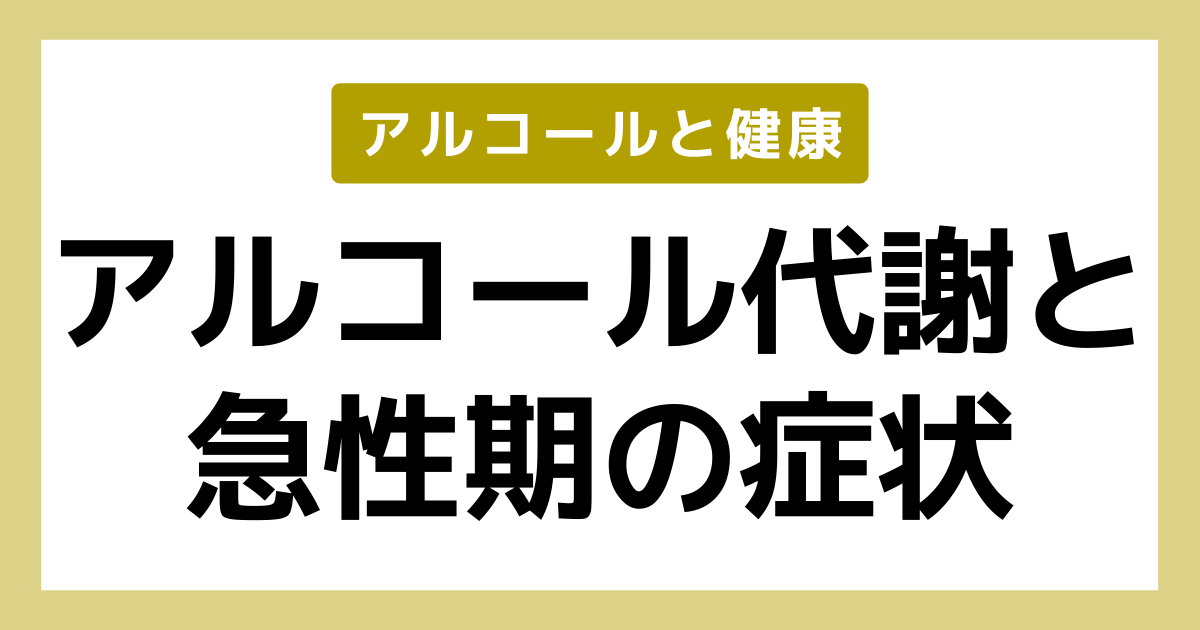
【アルコールと健康】#4 アルコールの代謝と急性期の症状
アルコールの吸収と代謝 アルコールの吸収 アルコールは胃ではゆっくり吸収されますが、小腸に入ると一気に吸収されてアルコール血中濃度が上がります。そのため、空腹…
臓器 編
-


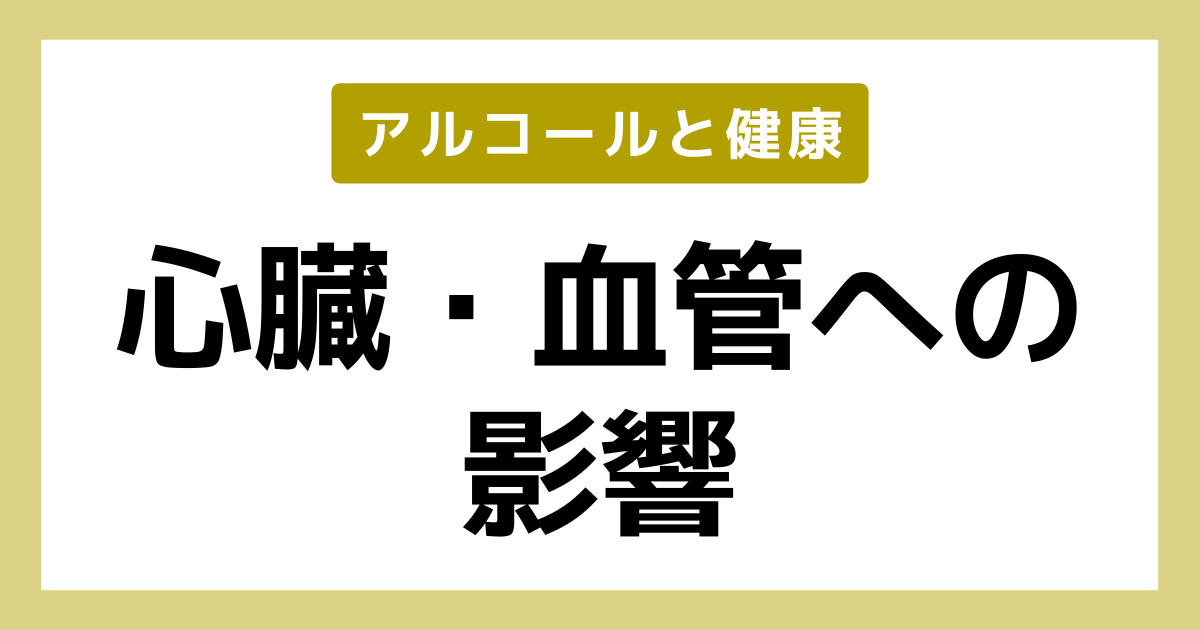
【アルコールと健康】#5 アルコールと心臓・血管
高血圧・心臓病のリスクを上げる ライフスタイルと心臓病について検討した研究※1では、過度に飲酒をする人たちは顕著に高血圧と冠動脈疾患(狭心症や心筋梗塞)のリスク… -


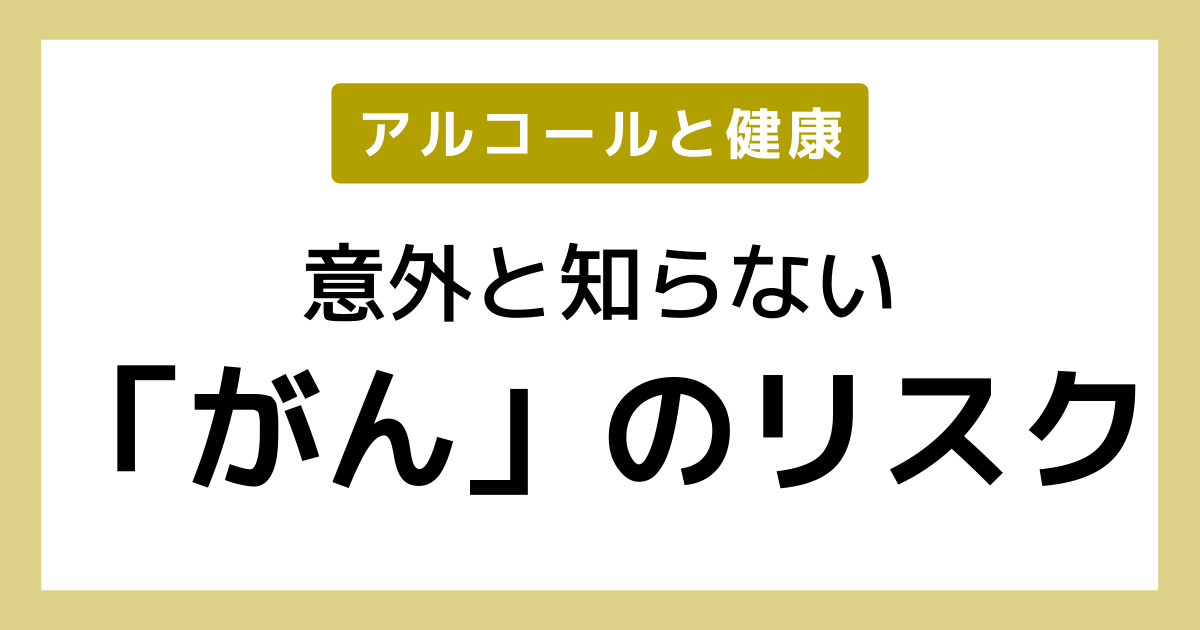
【アルコールと健康】#6 アルコールと「がん」
アルコールと「がん」の関係 多くのアルコールを習慣的に飲んでいる方に、がんの発生が多いことがわかっています。そして、飲む量が多いほどそのリスクが高くなっていき… -


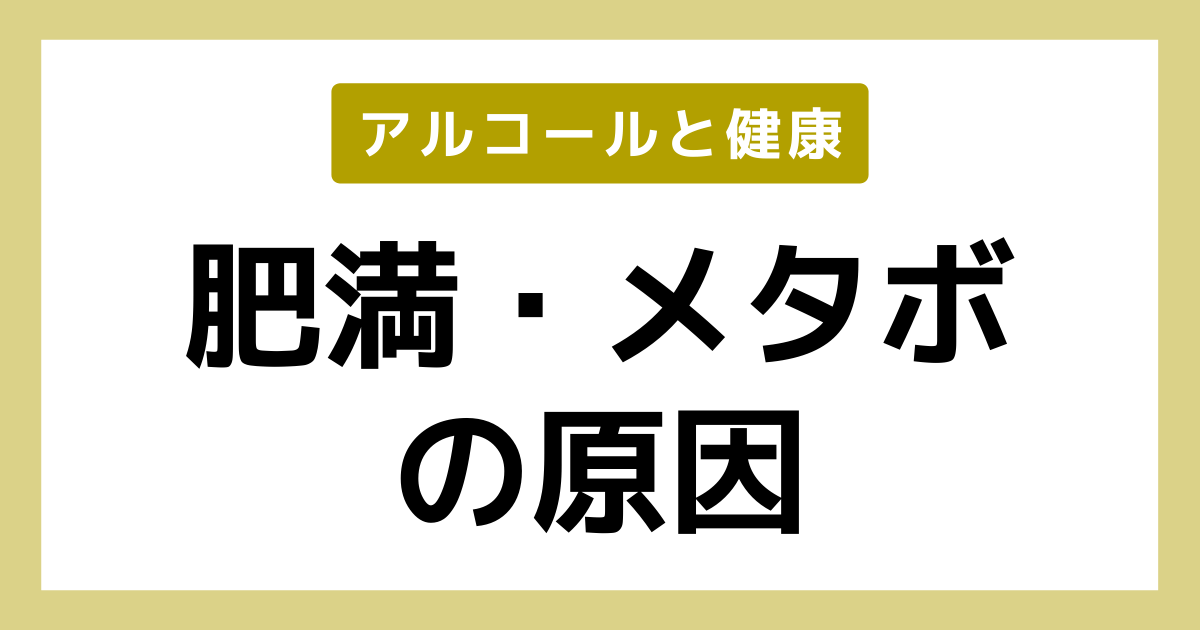
【アルコールと健康】#7 アルコールと肥満・メタボ
アルコールを飲むと太ることはよく知られています。 特にビール腹という言葉があるくらい、飲酒習慣がある方はお腹がぽっこりする傾向にあります。ぽっこりしたお腹は内… -


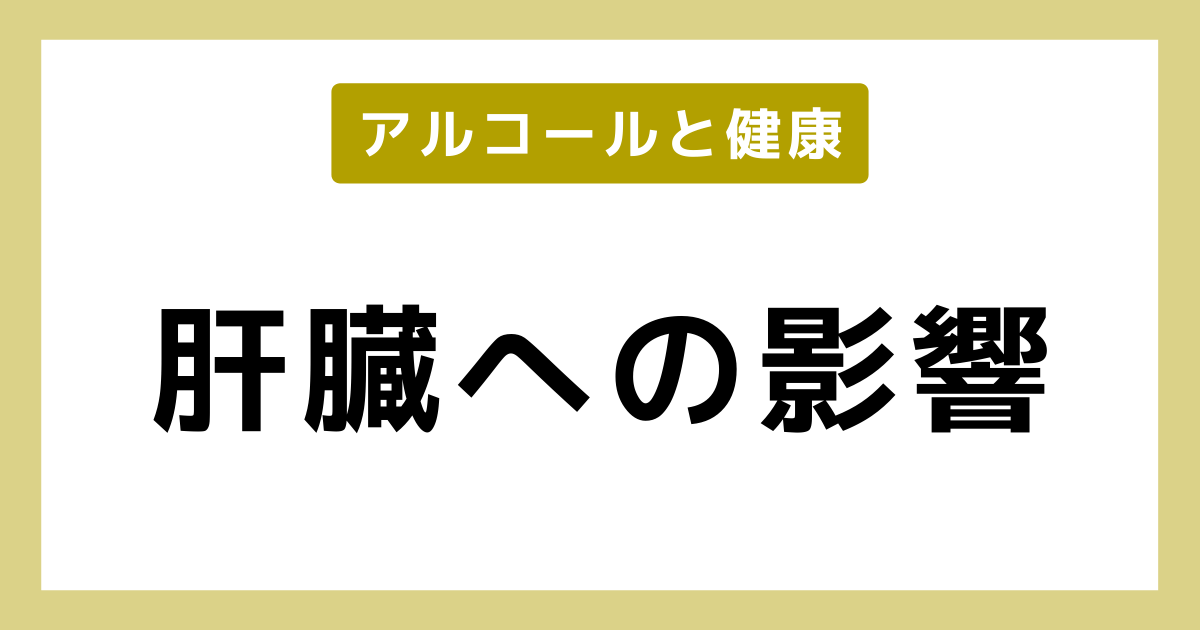
【アルコールと健康】#8 アルコールと肝臓
脂肪肝・肝炎・肝硬変 【アルコールによる肝臓の病気】 アルコール性脂肪肝 アルコール性肝炎 肝硬変 肝臓がん STEPアルコール性脂肪肝 アルコールにより肝臓でトリグリ… -


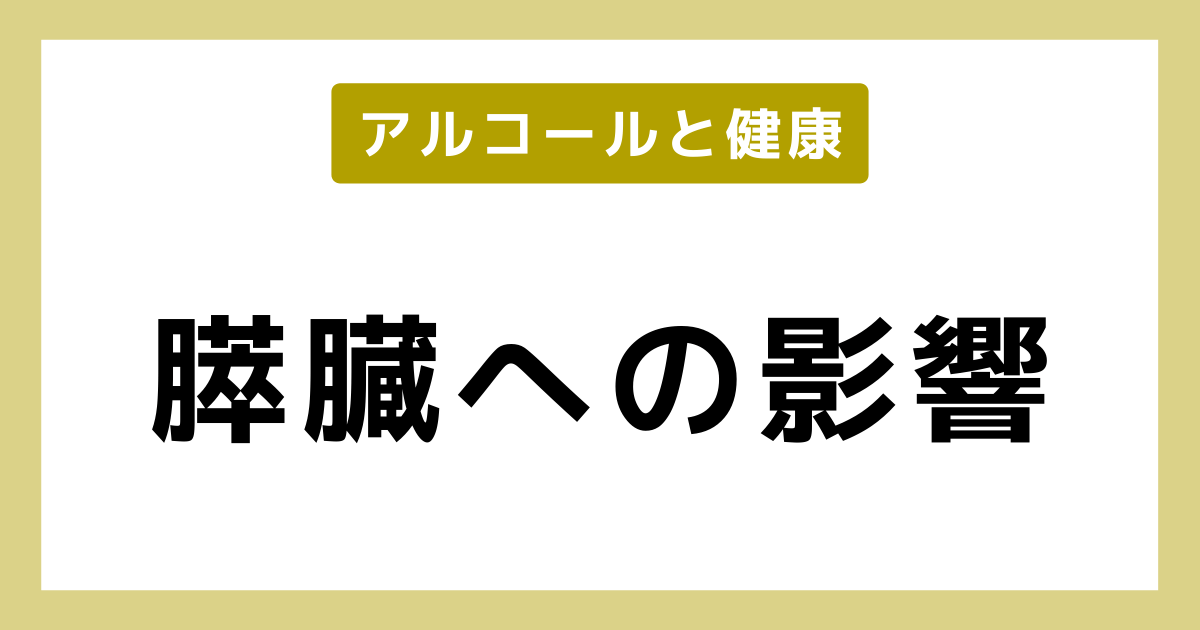
【アルコールと健康】#9 アルコールと膵臓
膵臓(すいぞう)は、胃の後ろにあり多くの役割を持つ大事な臓器です。以下に膵臓の役割を示します。アルコールは膵臓に炎症を引き起こし、膵臓の働きを低下させる恐れ… -


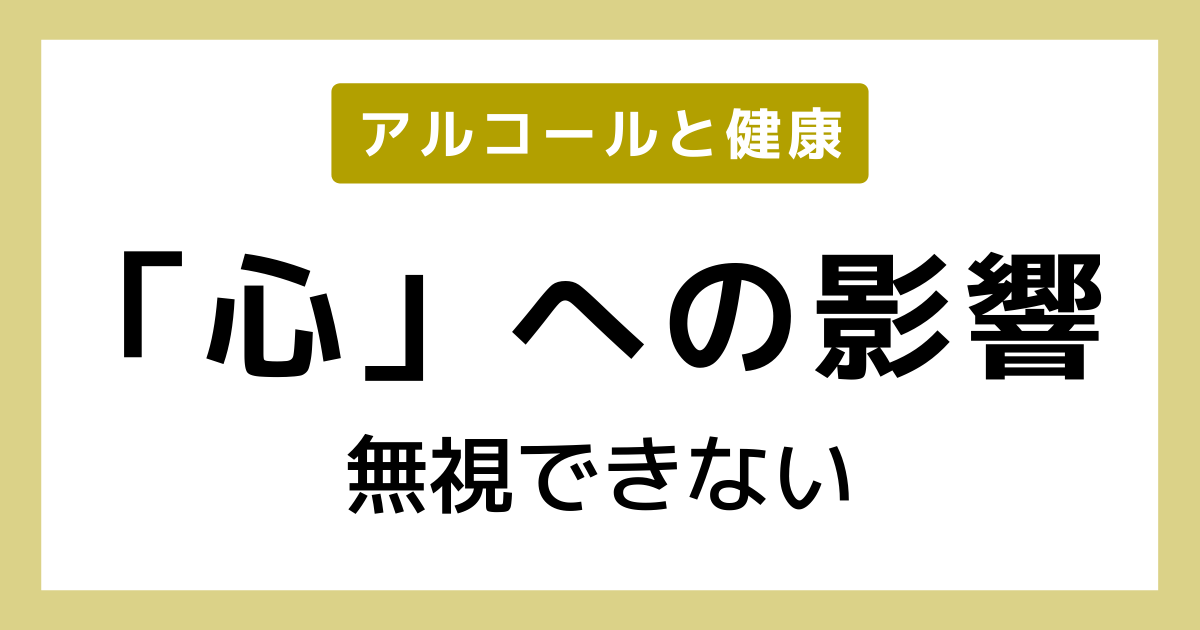
【アルコールと健康】#10 アルコールと「こころ」
アルコールの脳への影響 アルコールは脳の働きに影響する 脳は大きく下記のように分けられ、それぞれに重要な機能があります。 大脳皮質:理性をつかさどる 大脳辺縁系… -


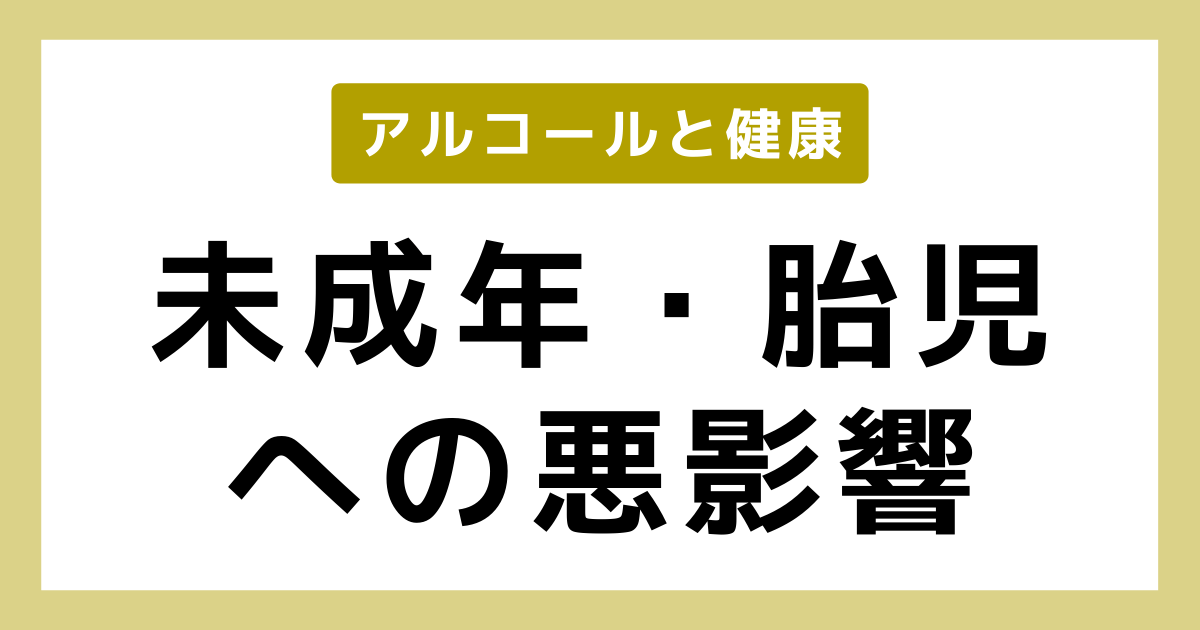
【アルコールと健康】#11 アルコールの未成年・胎児への悪影響
未成年への影響 20歳未満の人はお酒を飲んではいけません 日本の法律『未成年者飲酒禁止法』にて20歳未満の飲酒は法律で禁止されています。それは、身体的・精神的な発…